この記事にはPR広告が含まれています。
3・4歳(新年少)の生活を見直すきっかけに|ちゃれんじリストの内容と家での取り組み
2022年5月27日

進級前に届いた3・4歳向け「こどもちゃれんじ・ほっぷ」のお試し教材。
その中に「3・4さいのちゃれんじリスト」というがんばりポスターがありました。

新年少さん向けに15のチャレンジ項目が設定されているこのポスター。
子どもの生活習慣やマナーについてふり返ったり、新しく挑戦したいことを考えたりするきっかけになりそうだと、3か月ほど目につく場所に貼っていました。
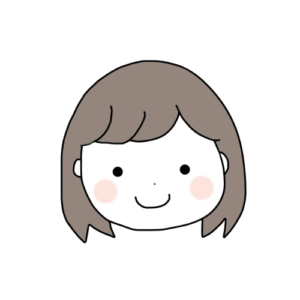
定期的に子どもへの声かけやかかわりを見直せてよかったです。
この記事では、「3・4さいのちゃれんじリスト」の項目内容と、リストの内容を達成するためのに取り組んだことの一例をまとめています。
- 3・4歳が家庭でがんばりたいことの例を知りたい
- 家庭での取り組みの具体例が知りたい
このような人のヒントになれば嬉しいです。
無料でもらえるお試し教材や発達に沿った保護者向け冊子は、子育てのお役立ち情報もりだくさん♪
気になる人は、【こどもちゃれんじ】のHPから資料請求してみてくださいね。
目次
3・4さいのちゃれんじリストの内容は15項目
新年少の子供向けに届いた15の「ちゃれんじリスト」の内容は次のとおり。
ひらがな・数、生活編、気もち・ルール・マナー編のそれぞれのカテゴリーで5項目ずつ挙げられていました。
ひらがな・数にかかわること
年少期は、自分の名前や友だちの名前をきっかけに「ひらがな」に興味をもつお子さんが増える時期。
- 「ひらがなはっけんめがね」でひらがなを見つける(お試し教材)
- 「ひらがなはっけんずかん」で動物をさがす(お試し教材)
- 家の中にある数字を見つける
- おでかけ中にひらがなを見つける
- 「ひらがな・かずパソコンみほん」でひらがなクイズにこたえる(お試し教材)
お試し教材を使った項目以外にも、家や外出先で文字に興味を向けられるような項目がありました。
我が子の反応は…、こちらが声をかければ楽しんでやるという感じで、まだまだ文字にそこまでの興味はないようです。



子どもの興味の芽を待ちながら、気長にやっていきます。
生活にかかわること
生活編では、「自分のことは自分で」やりたい気もちが育ってくる時期ということで、次の項目が挙げられていました。
- 朝の着替えをひとりでやってみる
- ごみはゴミ箱に入れる
- 家に帰ってきたら手を洗う
- おもちゃは使い終わったら元の場所に戻す
- 早寝・早起きをがんばる
気もち・ルール・マナーにかかわること
公共のルールの大切さも理解できるようになる年少期。
- いただきます・ごちそうさまを言う
- 道を歩くときはおうちの人と手をつなぐ
- 朝起きたらおうちの人に「おはよう」を言う
- 玄関で脱いだ靴を並べる
- お店の人に「ありがとう」を言う
あいさつや外での行動についての項目が挙げられていました。
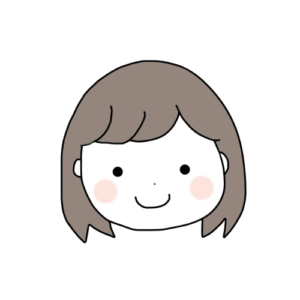
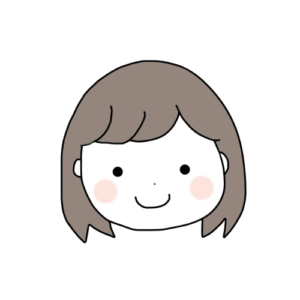
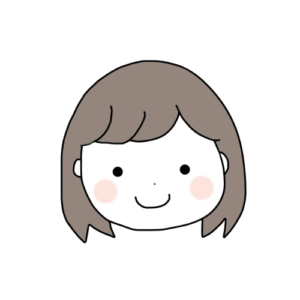
どれもしっかり身につけたい習慣ばかりですね。
子どもと一緒に家庭で取り組んだことを紹介
ここからは、リストの項目について、我が家でやってみたくふうや声かけをまとめています。
もちろん、リストの内容に縛られる必要はないと思うので、これからも子どもとの時間を楽しむためのヒントとして使っていきたいと思っています。
書き出してみると、当たり前に感じることも多いのですが、日々の生活に追われているとやってなかったかも…と反省することも。



現在も取り組み中のもの、試行錯誤中のものばかりですが、長女との記録として残していきます!
1.ひらがな・数にふれる
まだまだ文字への興味は薄そうな我が子ですが、ワークやおもちゃで遊んでいるときは「これは何?」とひらがなの質問をすることが増えてきました。
お名前シールやカレンダーなど身の回りの文字や数にも目を向けられるように声をかけています。
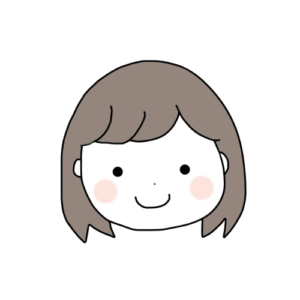
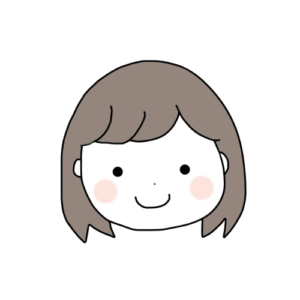
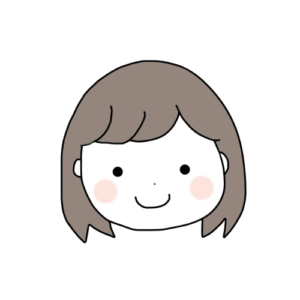
今、我が家で文字への興味のきっかけになっているのは、Z会とひらがな積み木です。
Z会を受講スタート
毎月少しずつ文字にふれることができるZ会のワーク。
その場かぎりの興味で終わることが多いですが、「しかの“し”だね。」など言葉とつなげるようにしています。
「しろくまも“し”だよね。」など言葉見つけに広がるのも楽しいです。
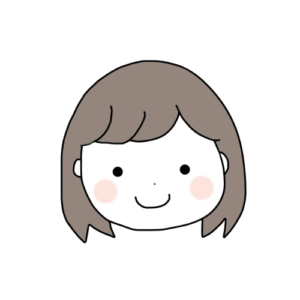
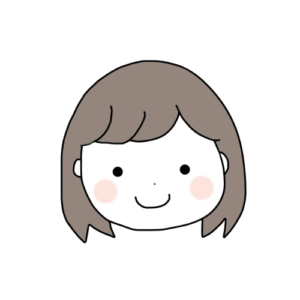
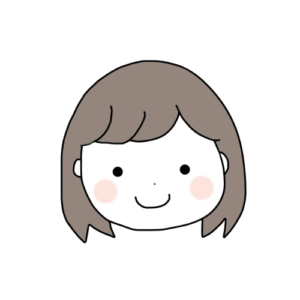
我が家にはちょうどいい量のワークで、少しずつ取り組んでいます♪
文字を使ったおもちゃ
リンク
子どもが2歳になったときにもらったひらがな積み木も少しずつ活躍するように。
今は、ひらがなポスターの近くの棚に置いています。
文字に興味がないときには、積み木として使うだけでしたが、最近は、絵を見て「これは、さるの”さ”。」と言ったり、適当に並べた文字を「何て読む?」と聞いたりすることが増えました。
2.服を自分で選びやすい場所に収納する
- あさの着替えをひとりでやってみる
この項目に取り組みやすくするために、子どもが自分で服を取り出せるように配置を見直しました。
見えるように並べる
基本的にはウォークインクローゼットに服をかけて収納している我が家。
備え付けのポールでは子どもが届かないため、背の低いハンガーラックに子ども用の服をかけるように。
リンク



自分で服を選ぶのは楽しそうだし、「これ、イヤ!」と言われるストレスも減りました。
気候やその日の予定に合わせて声はかけますが、基本的には子どもにお任せできるようになりました。
服が汚れたときなども自分で着替えているところを見ると成長を感じます。



自分でできる環境をつくるって大事ですね。
引き出しにラベルを貼る
子ども用のパジャマ・下着・靴下・ハンカチ・かばん・ぼうしなどは、チェストに収納しています。
リンク
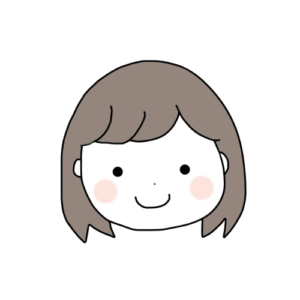
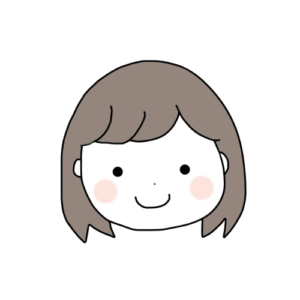
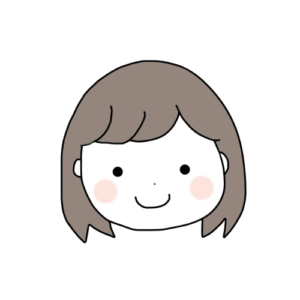
すっきり見える明るい色が気に入っています。
子どものものは、取り出しやすい下段にまとめ、イラストと文字で簡単にラベリング。
お風呂上がりの着替え、お出かけセットの用意など、ものの場所が自分でわかるようになると、子どもが自分で動けることが増えました。
3.ものの定位置を子どもと確認する
- ごみはごみ箱に入れる
- おもちゃは使い終わったら元の場所に戻す
上記の項目を見て、ごみ箱やおもちゃなど、子どもに関係のあるものの定位置を伝えることも気をつけるようになりました。
ものを移動させたら場所を共有
次女の何でも口に入れる時期、引っ張り出したい時期などに合わせて、定期的にものの置き場所を変えることがあります。
例えば、ごみ箱。現在、我が家では床置きの小さいごみ箱を使っていません。
床置きのごみ箱を片づけるときに、「これからはここに捨ててね。」と長女に捨てる場所を伝えました。
決められた場所に捨てられる日、そのまま放置されている日…とムラはありますが、【○○に捨てる】という共通認識があるので、声かけ後はわりとスムーズに動けることが多いです。



小さい子どもほど、【おやくそく】として決め事や変更点を伝えるのって大事なのかもしれませんね。
おもちゃは一軍だけリビングに
おもちゃはほとんど買わない我が家ですが、それでもプレゼントやおまけの品、お下がりなど、新しいおもちゃが家にやってくることも。
よく遊ぶ一軍のおもちゃだけをリビングに残し、それ以外は子ども部屋のクローゼットに片づけています。
おもちゃを厳選することで次のようなメリットを感じています。
- 子どもがおもちゃを選びやすい
- 一つの遊びに集中しやすい
- 元の場所に戻しやすい



おもちゃ収納は、定期的に見直したいものの一つです。
4.あいさつは大人から♪とにかく言い続ける
- いただきます・ごちそうさまを言う
- 朝起きたらおうちの人に「おはよう」を言う
個人的に大切にしたいと感じたあいさつの項目。



朝のおはよう、あんまり意識できていなかったかも…!
子どもとあいさつを交わすというより、こちらが「おはよう。さあ、準備するよー!」という感じで朝から一方的に声をかけていたなと反省。
はじめのうちは、「おはよう」を言うのが恥ずかしそうだった長女ですが、毎日続けていると自分から「おはようー」と起きてくるように。
ちゃれんじリストがいいきっかけになりました。
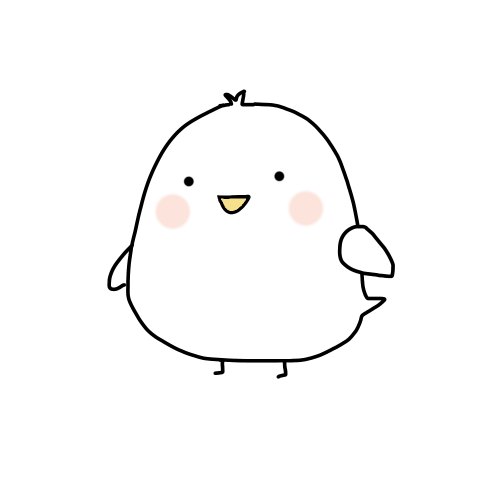
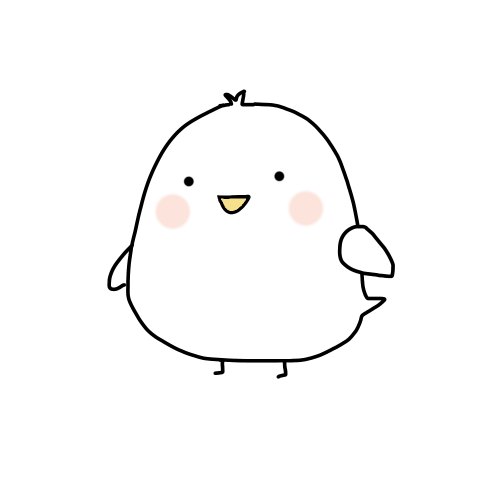
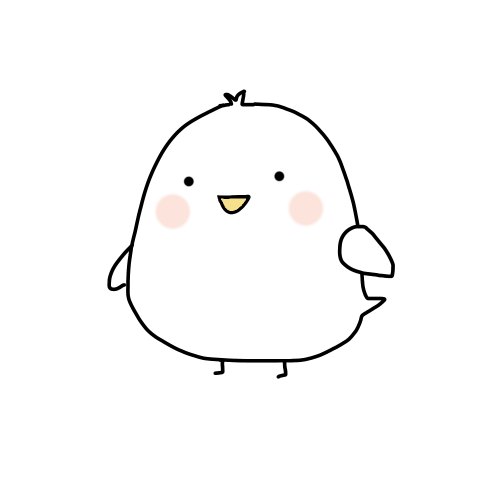
朝からあいさつがあると気持ちがいいよね。
余談ですが、たまたま見かけた芦田愛菜ちゃんに関する記事でも、あいさつに関する内容がありました。
- おはよう
- さようなら
- ありがとう
- ごめんなさい
- わかりません
- お願いします
- 知りません
芦田愛菜の「医学部内定」報道で証明された“両親の教育法”が完璧すぎる! 神童を育てた「7つの言葉」 (msn.com)
上記の「7つの言葉」を言えるような子になることを大切にされていたそうです。



愛菜ちゃん、とってもいい子そうでテレビに出ているとつい見てしまいます。
あいさつは、毎日何気なくかわす一言だからこそ、これからも意識していきたいなと感じました。
5.子どもが自分でやってみる機会をつくる
- 自分の身の回りのこと
- 公共の場所でのルール
- あいさつなどのマナーなど
やらせてみたいことはある一方で、大人が準備した方が早い、子どもが動きやすい環境づくりが大変…となかなか重い腰が上がらないことも。
しかし、子どもが自分でがんばろうとしている姿を見るのはやっぱり嬉しいし、子どもが得意げになるのもかわいいです(笑)
はじめから完璧を目指したり、ハードルが高かったりすると、大人も大変なので、次のような流れで少しずつ子どもが挑戦できるように気をつけています。
- 自分でやってみる機会をつくる
- 少しでもできたところを認める
- うまくいかなかったところは、どうすればいいか一緒に考える
これからも、子どものいろいろなチャレンジを応援していきたいです。



そのためにも…子どもがやってみることを受け止められる心のゆとりと、動きやすい仕組みづくりは大切ですね。
まとめ:子どもを認めるきっかけをたくさん見つけたい
この記事では、【こどもちゃれんじ】のDMで届いた「3・4さいのちゃれんじリスト」の項目内容と、リストの内容を達成するためのに取り組んだことの一例をまとめました。
3・4さいのちゃれんじリスト
- 「ひらがなはっけんめがね」でひらがなを見つける
- 「ひらがなはっけんずかん」で動物をさがす
- 家の中にある数字を見つける
- おでかけ中にひらがなを見つける
- 「ひらがな・かずパソコンみほん」でひらがなクイズにこたえる
- 朝の着替えをひとりでやってみる
- ごみはごみ箱に入れる
- 家に帰ってきたら手を洗う
- おもちゃは使い終わったら元の場所に戻す
- 早寝・早起きをがんばる
- いただきます・ごちそうさまを言う
- 道を歩くときはおうちの人と手をつなぐ
- 朝起きたらおうちの人に「おはよう」を言う
- 玄関で脱いだ靴を並べる
- お店の人に「ありがとう」を言う
DMの一部ということで、教材のおためし見本のための項目もありますが、年齢に合った生活習慣を見つめ直すいいきっかけになりました。
リストの内容には、すでにできていることもあれば、あまり意識できていなかったところも…。
今回、リストにある行動に注目したことで、子どもの行動を認める機会が増えました。
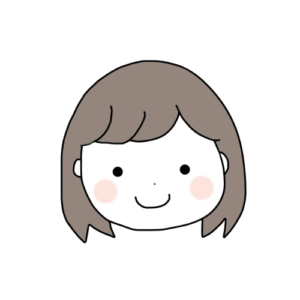
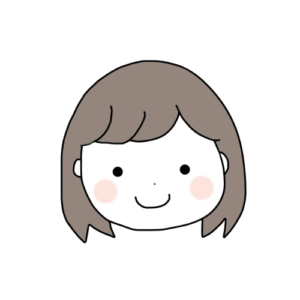
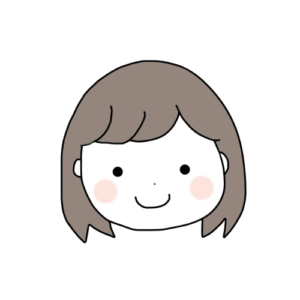
私自身も、子どもに次のような言葉をかけることが多くなった気がします。
- ありがとう。
- 助かるよ。
- ○○したら、嬉しいね。(気持ちいいね。)
ポジティブな言葉かけが増えると、目に見えてやる気を出す長女を見ていると、認めることって大切だなと実感。
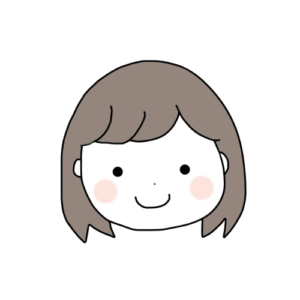
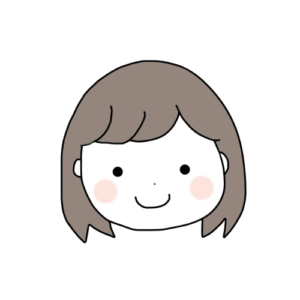
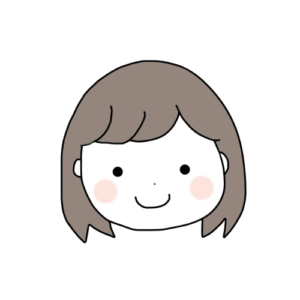
子どもを認めるきっかけを増やして、大人も子どもも笑顔で過ごす時間を増やしていきたいです♪
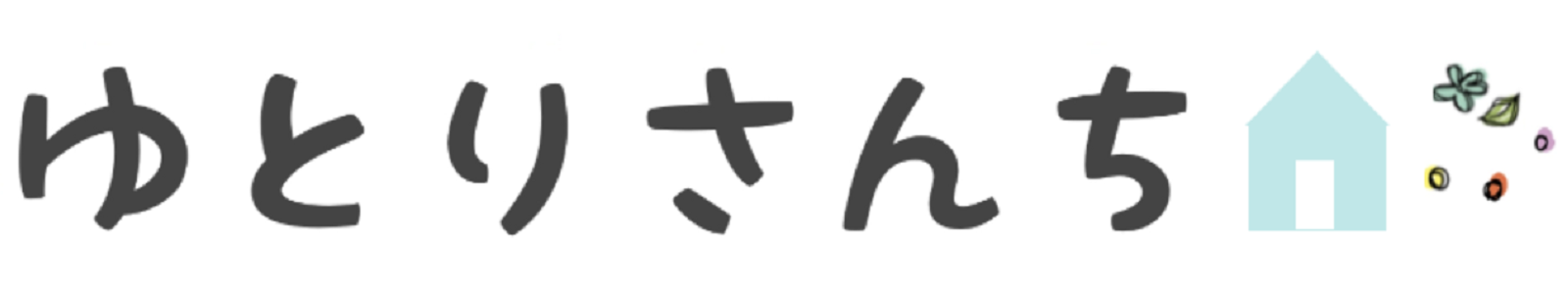
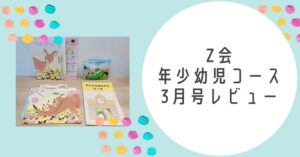
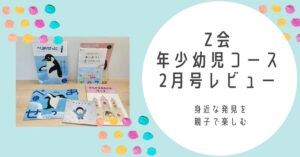
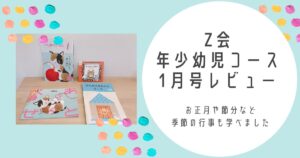
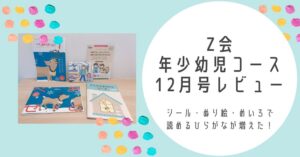
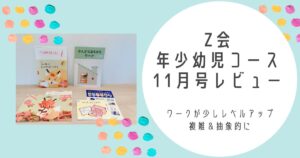


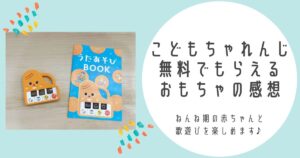
コメント